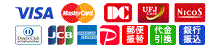臨書手本の学び方
古典の臨書最初のハードル
「古典を臨書しなければ、書は上達しない」といわれます。
また「臨書が出来ないものに、創作はできない」ともいわれます。
言い換えれば、「臨書が出来ないと、作品づくりはおろか、書の上達もおぼつかない」ということになります。
臨書するために古典作品をながめてみても、漢字の場合、普段あまりなじみのない拓本の文字が並んでいるのに困惑することもあるかもしれません。
しかも古い資料のため、欠けている部分や断裂したものもあって、鮮明でないこともあります。
とくに独学の場合は、市販の本を頼りに学びますが、中国法書選や書跡名品叢刊のような本を見ても、どう取り組んでよいか戸惑ってしまうことがあります。
初心者の方が臨書するには
さて、ここで学ぶことの意味を考えてみましょう。
「学ぶ」ということは「まねぶ」から転化した言葉で、「教わる通りに真似をする」という意味があります。
ですから、書道の練習も「まねる」ことからはじめてみてください。
書道が上手な人をまねることです。
しかし初めての人にとっては、いくら「まねぶ」といっても、古典を見て直接臨書するのは抵抗があると思います。
そこで先生から肉筆の手本で臨書するということになります。 自分よりも技量のすすんだ人の臨書を参考にすると、学びやすくなります。
独学の方は、書道技法講座などの本で、著者の臨書例が掲載されていますので、それを参考に臨書します。
直接、古典を手本に臨書するのが望ましいですが、前段階としてお手本による臨書から取り組むとよいと思います。
臨書の手本について
臨書のお手本は、古典の資料を人(たとえば書道教室の先生)が、自分の解釈と技量で臨書して手本にしたものです。
ということは、
この手本には、その人のフィルターを通って生まれたお手本ですので、古典の資料とはまた別物です。
それが全てではないということです。
ですが、習い方の順序として、まずその臨書の手本でしっかりと学ぶことが大事です。
そして、その手本のもつ技術を習得出来るように努めてください。
それが臨書のまず第一の段階です。
それを時間をかけて何度も繰り返すと、自然とその手本に近づいていきます。
しかし、実際に自分の目で古典を見、自分の考えで表現したものではありませんから、それで終わったと考えない方がよいと思います。
それはあくまで先生の臨書に近づいたという認識をもつべきです。
しかし、人の手を借りて、古典の理解に一歩近づいたことには変わりありません。
臨書の手本を学ぶ事は、臨書の方法を学ぶことと同時に、用筆の基本や運筆の方法を実際に体得することができます。
そして、練習を深めていくにつれて、形の取り方、まとめ方、さらに線質の錬磨などにもたいへん役立ちます。
つまり、手本を学びながら、書道の基本を学ぶことができるのです。
そして、さらに進めば、臨書の手本のもとになる古典の事や文字の特徴、それを書いた人物について、またその書かれた内容や事柄、時代背景など、知識が多方面に広がり、書道の理解を深めることができます。
手本の臨書について注意点
しかし、逆に陥りやすい面もあります。
それは、臨書の手本で練習することが習慣化してしまうことです。
古典を見ることができなくなって、手本なしでは書けなくなることです。
それは書道の上達を停滞させてしまうばかりか、型にはめ込んでしまい、とらわれた書道しか出来なくなってしまう恐れがあります。
このようなことがないように、ある程度自信がついてきた段階で、古典に取り組んでみてください。
自分の目で、自分の感性で、自分の力で古典を臨書してみてください。
古典にチャレンジするタイミングを見極めるのは難しいですが、臨書の手本通りに書けるようになったと思った時、また先生が評価してくださるようになれば、古典の臨書を試してみてはいかがでしょうか。
臨床手本を学ぶ
実際に臨書の手本を学ぶ上で、その順序や大事な点をあげていきます。
1.徹底的に学ぶ
まずはその臨書の手本が良いものか、悪いものかなどは考えないで、絶対的なものとして、徹底的に学んでみてください。
細かなところから全体まで。
2.細かく大胆に
両極にある言葉ですが、まず最初は細かな点も注意しながら臨書します。
点画・用筆形・まとまりなど。
ある程度手本を見なくても書けるようになったら、思い切って大胆に書いてみてください。
筆力・筆勢を意識して。
3.繰り返し学ぶ
何回も繰り返し臨書します。
練習の基本は、やはり繰り返すということです。
4.多くの古典を学ぶ
同じ課題ばかりを学ぶというのは、そこから得られる気づきもあるのですが、どうしても変化に乏しく飽きてしまいがちです。
ですから、なるべく異なる課題に取り組むことも継続して臨書するには必要なことではないでしょうか。
また古典も1つのものではなくて、同じ書体でも別のもの、あるいは別の書体のものも順次学んでいくことは大事なことです。
5.道具選び
墨の濃さや量、紙質などにも気をつけましょう。
まずは書きやすい墨や紙を基準にして、いろいろなものを試してみてください。
先生や仲間、専門店で聞いてみるのも大切です。
以上、臨書のお手本についてご説明いたきむした。
臨書の手本は、書く人が違えば、同じ古典の臨書であっても、全く内容が異なる場合がありますから、ひとつの手段として取り組んでみてください。
臨書手本を学ぶための10のポイント
1.徹底的に学ぶ
2.細かく大胆に臨書
3.繰り返し学ぶ
4.多くの古典を学ぶ
5.道具を選ぶ
6.大きさを変えて書く(小さく書く・大きく書く)
7.全臨する(古典一冊全てを臨書すること)
8.古典の書かれた内容を知る
9.古典の筆者や書かれたいきさつを学ぶ
10.条幅の作品に仕上げる