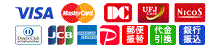中国の書学を研究する上で、必要と思われる基礎的な文献入手についてまとめ、実際に研究していく手順の一例をあげます。
■検索・入手方法
書名を知っている場合
最寄りの図書館のホームページで検索し、各図書館・各研究室で本を入手。
書名を知らない場合
対象の書名が未知、不明の時は、自分なりの項目を仮にたてて、図書館のホームページで任意検索します。
たとえば、「中国の歴史」について知りたい場合、その項目、あるいは、「歴史」「中国」で検索します。
または係員に相談する。
現在容易に手に入るもの
1.和書について
インターネットの検索エンジンで検索して無い場合、和書は「日本書籍総目録 書名編・索引編」(日本書籍出版協会発行)を使って調べるとよいです。
1977年から年刊されていて、現在入手できる本のほとんど全てが網羅されています。
同様の本に「全日本出版物総目録」(国立国会図書館編・年刊)、「出版年鑑」(出版ニュース社・年刊)「日本総合図書目録」(日本書籍出版協会・年刊)などがあります。
「国書総目録」(岩波書店)には、1967年以前に日本で発行された現存図書名が載っており、所蔵文庫、図書館名が記入されています。
新刊書について知るためにはこれらでは間に合いませんので、「出版ニュース」(出版ニュース社)「納本週報」(国立国会図書館)を参考にしてください。
2.中文書(中国の出版物)について
神田の東方出版さんから発行されている月刊のPR誌「東方」が便利です。
3.中文書(台湾の出版物)について
琳瑯閣書店さんから刊行されている「輸入書最新入荷速報」が便利です。台湾の各書店別の目録も参考になります。
現在容易に手に入らないもの
古本については古書目録、古本市、古本屋で買い求めるしかありません。
唐本、貴重書などについては、叢書に収蔵されているかどうか調べます。
「叢書大字典」(南京辞典館)「中国叢書綜録」(上海古籍出版)が便利です。その本が叢書類に所収されている場合は「叢書集成」「四部叢刊」「四部備要」「欽定古今図書集成」「国学基本叢書」などを参照してください。
叢書類に所収されていない場合は、大学の図書館などでコピーするなど必要な書類を揃えます。
研究するには、対象の基礎知識が必要ですので、基本的用語、専門語は必須です。
該当の書道史、書道概論を学ぶようにしましょう。